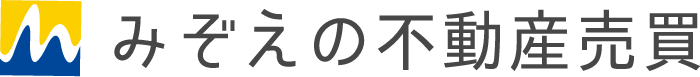NEWS
新着情報
2025.08.21
遊休不動産が「蓄電所」になる可能性
最近、田舎の資産価値の低い不動産にも問い合わせいただくケースがあります。
以前の問い合わせと違い「蓄電所用の土地」として利用したいとのことです。
プレハブのような箱に蓄電施設を設置するタイプで300坪以上であれば十分に事業として成り立つようです。
そんな中、大手住宅メーカーである大和ハウス工業が、「系統用蓄電所事業」に参入するという記事を読みました。
これは、遊休不動産を活用する新たな選択肢になる可能性があるため、非常に注目すべき動きだと感じます。
蓄電事業、儲かりそう!!というわけで素人なりに調べてみました。
1. 蓄電事業の基本
蓄電事業とは、文字通り電力を貯めておく(蓄電)事業です。
しかし、ただ電気を貯めるだけでなく、それを必要な時に使うことで、収益を得たり、社会に貢献したりすることが目的です。
家庭用の蓄電池は、主に自宅で発電した太陽光電力を貯めて夜間に使ったり、停電時の非常用電源として利用したりします。
一方、大和ハウス工業が参入するのは、より大規模な「系統用蓄電所」です。
これは、電力会社が管理する大規模な送電網(電力系統)に直接接続される蓄電施設です。
2. なぜ「系統用蓄電所」が必要なのか?
系統用蓄電所は、主に再生可能エネルギーの普及に伴う電力系統の課題を解決するために注目されています。
再生可能エネルギーの変動性への対応: 太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変動します。晴天の昼間は電気が余るほど発電し、曇りや夜間はほとんど発電できません。この変動が大きすぎると、電力の供給量と需要量のバランスが崩れ、停電の原因になる可能性があります。
「出力制御」の多発: 電力の供給過剰を防ぐため、電力会社は再生可能エネルギーの発電事業者に、発電を一時的に停止するよう要請することがあります。これを「出力制御」と呼びます。特に日照条件が良い九州地方では、太陽光発電の普及が進んだ結果、出力制御が頻繁に発生しており、せっかく作った電気が無駄になってしまうという問題がありました。
3. 系統用蓄電所事業の仕組みと収益モデル
系統用蓄電所は、これらの課題を解決しながら収益を上げる、いくつかのビジネスモデルを持っています。
① アービトラージ(電力価格の差を利用)電力は、市場で取引されており、その価格は時間帯によって変動します。電力需要が少なく価格が安くなる夜間や、太陽光発電で電気が余る昼間に電力を購入して蓄電します。そして、電力需要が高まり価格が高くなる夕方などに放電して売電することで、その価格差から利益を得る方法です。
② 需給調整市場への参加
電力の需要と供給のバランスを保つための市場です。電力系統の周波数を安定させるため、蓄電池が瞬時に充放電を行い、その調整力に対する報酬を得る。
③ 容量市場への参加
将来の電力供給力を確保するための市場です。蓄電所が将来的に供給できる電力量を事前に約束することで、その「供給力」に対して報酬を得ます。
これは、実際に電力を放電しなくても、待機しているだけで安定的な収益が見込める仕組みです。
このように、蓄電事業は、電力の安定供給という社会的な課題を解決しながら、再生可能エネルギーの有効活用、そして新たなビジネスとしての収益性を追求する、
非常に将来性のある分野です。
再生可能エネルギーの普及が進む日本において、電力の安定供給を支える蓄電所の役割は今後ますます重要になってきます。
不動産オーナーの皆さんにとって、これまでの常識にとらわれない新しい不動産活用モデルを考える良いきっかけになるのではないでしょうか。
「もしかして、うちのあの土地も使えるかも?」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
最新の市場動向を踏まえ、最適な活用方法をご提案させていただきます。
稲佐(090-7398-6669)
CONTACT
ご相談・お問い合わせ
九州・福岡の不動産売買のことなら「みぞえ」におまかせください
[ 受付時間 平日 [9:00 - 17:30 ]092-715-1451